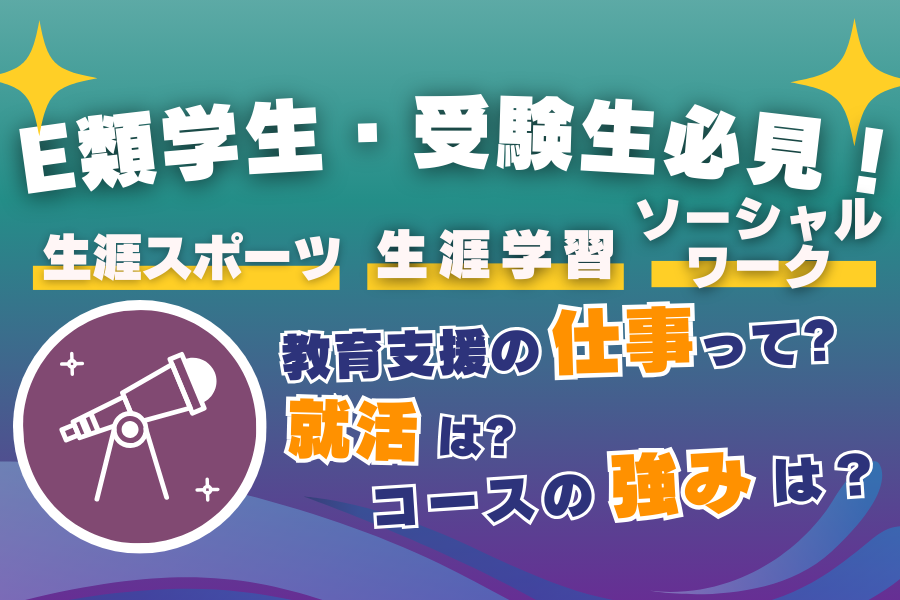
みちしるべ
おしえてE類の卒業生!教育支援職のキャリア②【キャリア支援課コラボ】
2025.09.29
 東京学芸大学公式ウェブマガジン
東京学芸大学公式ウェブマガジンみちしるべ
2025.08.28

「教員以外の道に就職した人たちってどんなことしてるの?」
「就活ってどんなことすればいいの?」
「教育支援課程の学びは仕事にどう生きるの?」
東京学芸大学には、教員以外の道で教育に携わる人々を育成する「教育支援課程(通称E類)」もあります。今回は2025年に2回にわたって開催された『教育支援課程の卒業生が語る オンライン キャリア・トーク』から、3人の卒業生の声をお伝えします。
— この記事は約10分で読めます。
岡本茉奈さん
カウンセリングコース卒業後、豊島区役所に入庁して4年目。教育委員会で家庭教育の支援に携わった後、現在は福祉部門に異動。ひきこもり支援を担当している。
在学時は専攻以外のコースの講義を積極的に受講し、そこで受けた「社会教育実習」で豊島区役所に出会う。
岡本さん:心理学に関心があって入学しましたが、E類の講義を受けているうちに、カウンセラーになるのはまだ早いかな?と。でも、大学での学びを生かせる仕事はしたいと考える中で、幅広い分野で人のために仕事をしたいのだと気付きました。それが公務員就職への原点です。23区の中から豊島区を選んだのは、当時文化芸術に力をいれていたのと、社会教育実習先でもあり、馴染みがあったからです。

岡本さん:ゼミで就職を選ぶ先輩が少なかったので、情報は自力で掴みました。また、キャリア支援課の就職相談で面接や論文を見ていただいたり、民間企業も受けながら面接の場慣れをしたりしていました。面接ノートを作り、どんなことを聞かれたか振り返りを必ず行っていました。また、「オンライン市役所」というネットワークも使って、公務員像のイメージをつかんでいました。
岡本さん:教員免許の取れない課程であること、カウンセラーの養成課程にいたことを伝えました。心理学で学んだことが生かせる福祉や健康に関心があることを発言にちりばめて、区役所に入ったらこういう部門に行きたい、と話しました。
岡本さん:業務をする上で教育支援の大切さを強く感じています。区民の方に何か説明するときに「どういう方法でアプローチをしたらこの人に響くかな?」と、コースで学んだ心理学の知識も生かせていますね。
キャリアを積むにつれて、他課との調整や、区と区民団体、上司と後輩との間で板挟みになることも多いけれど、E類で学んだ「つなぐ」、コーディネート能力が生きていますね。
―生涯学習コースでの学びが、業務の基礎を支えているんですね。
岡本さん:社会教育実習でお世話になった部署に配属されたり、講演会で松尾直博先生(カウンセリングコース)を講師にお呼びしたりもしました。また、ゼミの先生だった福井里江先生が、豊島区ひきこもり支援協議会の副会長なんです。今も一緒に仕事をさせていただいています。
山田侑樹さん
情報教育コース1期生。学芸大学大学院の教育AI研究プログラムに進学後、株式会社電通総研に就職しエンジニア5年目になる。現在は企業向けの生成AIのアプリケーション開発の仕事に携わる。
山田さん:学部2年生のころに大学院進学を決めました。講義が面白いと感じ、もっと学んでから社会に出たいと考えたんです。院進後、企業と共同研究する「フィールド研究」というインターンシップみたいな講義があって、そこで電通総研とつながりました。研究の中で私と企業でお互いの様子も分かっていたし、学んだことをそのまま生かしやすい環境だったので就職しました。
山田さん:就活の時、学芸大生って「アピールできることがない」って悲観しがちですけど、大学で勉強したことを話すだけで採用側には伝わるので、自信持ってほしいなと思います。学芸大生は優しい人が多いと思うので、落ち着いた雰囲気でいろいろ学ぶ経験は、仕事でも生きます。 実際、会社の人事と関わると学芸大生にポジティブな印象を抱いている人が多いです。
学生大生の強みは、「人の話を聞くこと」や「専攻以外の分野も理解する力があること」ですかね。教育を学ぶことで、そういった面が磨かれているのではないでしょうか。
山田さん:私も社会人5年目になり、新人や中途採用を受け入れることが増えました。そこで彼らがどんどん仕事ができるようになって、成長を見るのが楽しいです。教育学部での経験があるからかな。
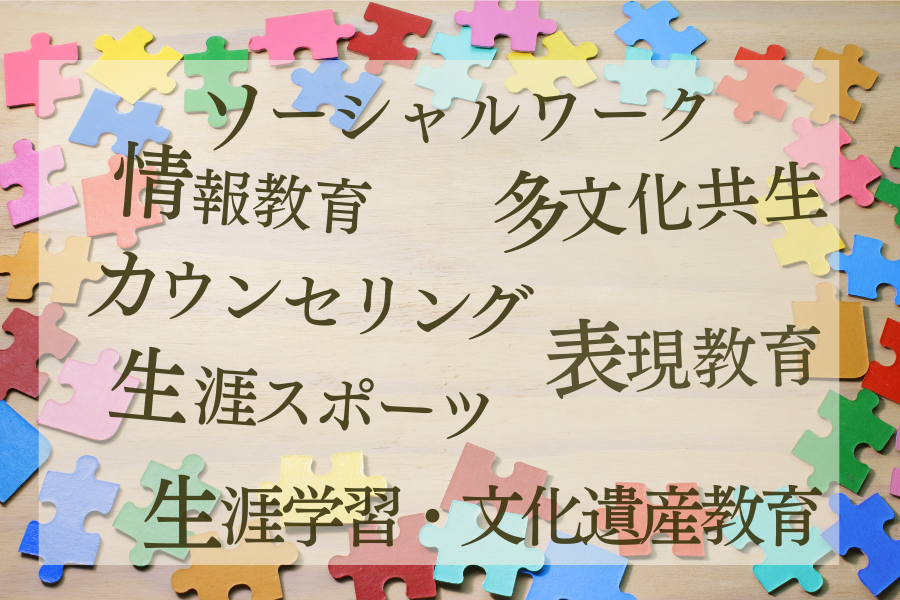
山田さん:当時は、「教育支援概論」(E類の他コースの学問を学ぶ)や「教育支援演習」(E類の他コース生とグループワークを行う)など、専攻以外の講義って少しめんどうだなーと思っていました。
けれど就職して研修の時に気づいたのですが、違う価値観の人と共同作業することが苦手な人が意外と多いんです。他の専攻の人と協働するあの授業がすごい役立ってるなあと感じます。
村松萌映さん
生涯学習コース卒業後、2024年に入庁し、労働政策課に配属。企業で働く人に向けたリスキリング※の支援や、仕事を探している人に向けた職業訓練などを担当。富山県は就職して初めて暮らした土地だが、あたたかい人に囲まれて楽しく生活中。
※リスキリング:働きながらスキルアップを目指すこと。
村松さん:2年生の春休みごろから周りでインターンシップの話が出てきて、そろそろかなと思いつつなかなか重い腰が動かず……という感じでした。
当時はオンラインが主流でしたが、実際に行ってみるのもいいなと思い、1~2か月ほど富山県庁で働くインターンシップに参加しました。これがよかったですね。インターンシップの最後に、県知事に私のプレゼンを聞いていただける貴重な体験になりました。みなさんも興味のあるインターンシップには参加することをおすすめします。
―インターンシップが現在の仕事を掴む場になっていたのですね。
村松さん:公務員と並行して民間企業も探さなければならなかったのですが、富山県という知らない地ということもあり難航しました。だけど富山県では「とやま女性活躍企業認定制度」や、大学生への企業紹介、インターンシップなどのイベントをやっているので、これらを活用しました。
村松さん:私は「学校以外にも教育の場はある」ことを伝えました。また、公務員にも協調性はとても必要なので、大学のグループワークで自分がどのように貢献したのかを伝えました。
インターンシップでの経験も聞かれるので、そこでしっかり自分をアピールするようにして乗り越えました。
村松さん:講義の中で、異なる専攻の人と発表資料を作ったことは役立っていますね。仕事だと初対面の人に電話したり一緒に仕事したりするのが当たり前なので、その度胸がつきました。E類での「人をつなぐ、調整する」といった経験が今役立っています。
村松さん:確かに責任が重い仕事って気が進まない、と感じることはあります。
でも、達成できた時は頑張ってよかったなと感じます。困った時も上司や同期が相談に乗ってくれるので、守られている安心感があります。自分もゆくゆくは誰かを支える立場になっていきたいですね。
教育支援課程の卒業生が語る オンライン キャリア・トーク第二弾の記事はこちら
執筆/居倉優菜
企画・取材協力/キャリア支援課
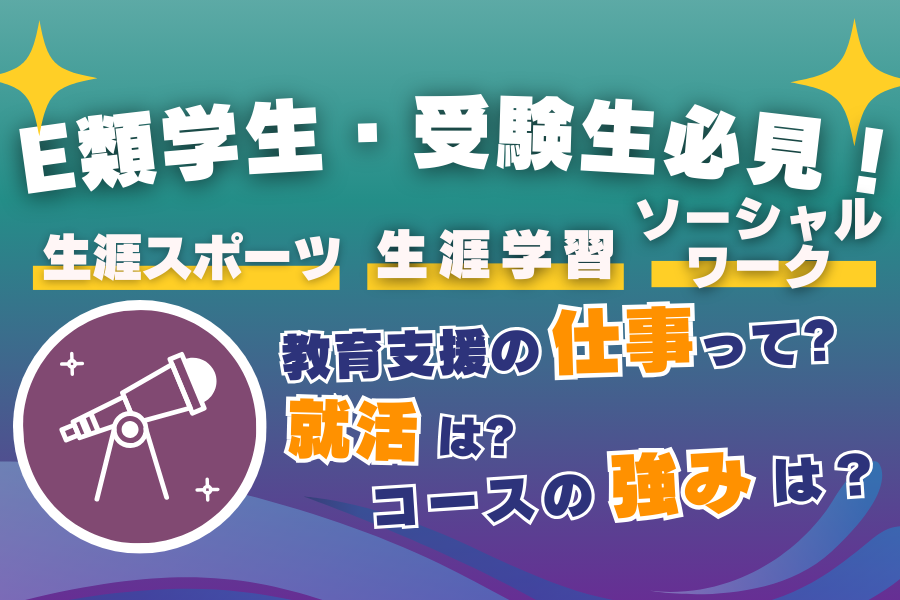
みちしるべ
おしえてE類の卒業生!教育支援職のキャリア②【キャリア支援課コラボ】
2025.09.29

みちしるべ
地域の力×企業の挑戦〜“ここ”だからできる、新たな学びに向かって〜
2025.06.26

みちしるべ
離島に広がるチャレンジの輪 ~生徒と創る “私たちの可能性”と向き合える場所~
2024.12.13

みちしるべ
絵本出版社で働く先輩に聞いてみた!〜「伝えたい」という変わらぬ思いが花開いた新しい道とは〜
2024.07.04

みちしるべ
アートが引き出す“自分らしさ” 感じたままに表現する機会を
2023.10.31

みちしるべ
「保健室」が存在しない国で行う養護教育
2022.12.26