
「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第13回 ゲスト:宮田諭志先生(成城学園初等学校 教諭)
2025.10.08
 東京学芸大学公式ウェブマガジン
東京学芸大学公式ウェブマガジン「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
2025.08.20
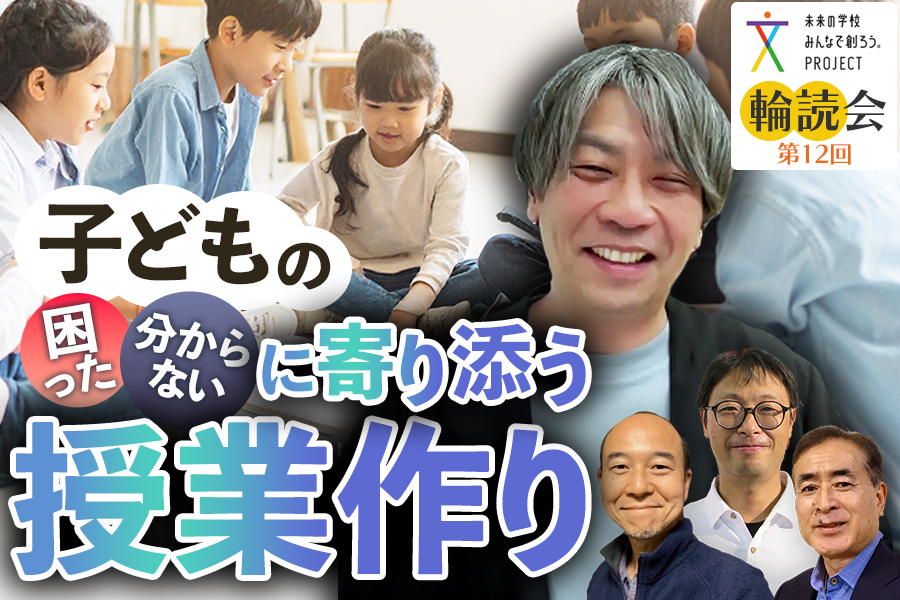
100人輪読会 第12回のゲストは、成城学園初等学校の教諭、楳原裕仁先生です。
楳原先生の実践の中心にあるのは、子どもの「困った」「分からない」に寄り添う授業作りです。単に「何が分からないか」を問うのではなく、「どうして分からないか」を軸に子ども同士の対話を促すことで、子どもたちが優しくなってきたとおっしゃいます。
授業においては、子どもたちの中に「相手意識」を育むことを重視されています。相手をリスペクトして「聴く力」が育つことで、丁寧で論理的な対話が生まれるとしています。
さらに、学びの環境における「居心地の良さ」と「安心感」の重要性も指摘されました。学校は教育の場であると同時に、子どもたちにとっての「居場所(コミュニティ)」であるべき。失敗が許される安心感の中でこそ、本当の学びが成立すると語られます。
そのために不可欠なのが「自己決定」の機会です。成城学園では、休み時間の過ごし方を子ども自身に委ねたり、低学年で「遊び」の授業を設けたりすることで、子どもたちの主体性を育んでいます。モチベーションを維持する要素として、「自己決定」「やれそうな予感(有用感)」「仲間の存在」の3つが挙げられました。
大人の役割は、子どもたちの活動を評価するのではなく、その一つひとつの行動を「価値づけ」てあげることだと強調されます。また、教育を「4年スパン」といった長い視点で見ることのおおらかさの必要性も提案されました。
最後に、教員自身も自らの指導法が「型」にはまっていないかを常に問い直し、「自分の根っこ」となるビジョンに立ち返ることの重要性が語られました。
楳原先生が最後に語る、楳原先生にとっての「未来の学校」とは?ぜひご覧ください。
輪読会に参加された方:
●楳原裕仁先生(成城学園初等学校 教諭)
●金子嘉宏先生(東京学芸大学教育インキュベーションセンター長 教授)
●荻上健太郎先生(東京学芸大学教育インキュベーションセンター 准教授)
●彦坂秀樹先生(東京学芸大学教育インキュベーションセンター 特命教授)
未来の学校 みんなで創ろう。Projectからの 「20の提言1st Season 2020~2022 ~完成しない、みんなで創り続ける学校を目指して」の詳細は、下記リンクからご確認いただけます。

「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第13回 ゲスト:宮田諭志先生(成城学園初等学校 教諭)
2025.10.08

「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第11回 ゲスト:小泉友先生(立川市立西砂小学校 教諭)
2025.04.22
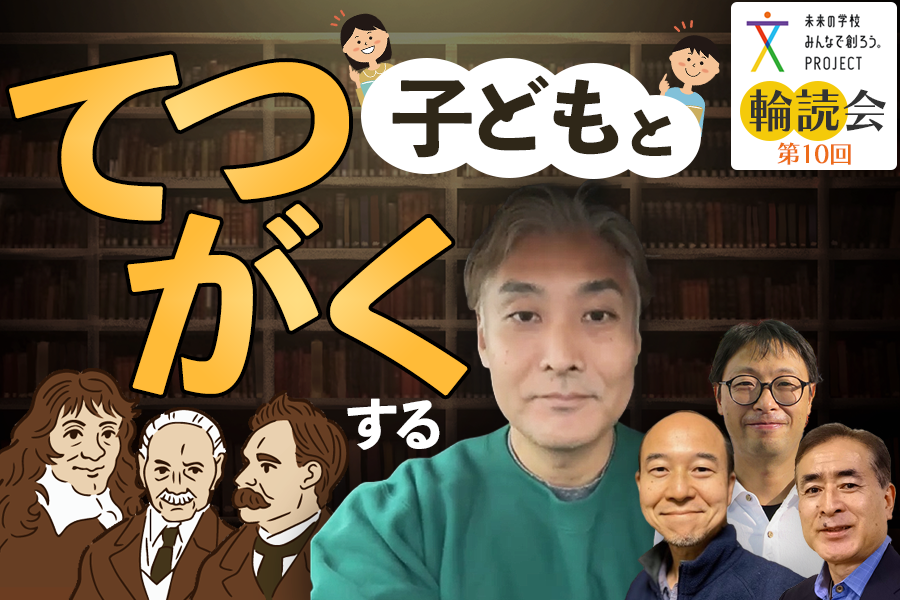
「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第10回 ゲスト:神谷 潤 先生(お茶の水女子大学付属小学校 教諭)
2025.03.18

「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第9回 ゲスト:下花剛一さん(株式会社ジョルテ 代表取締役 社長)
2025.02.05
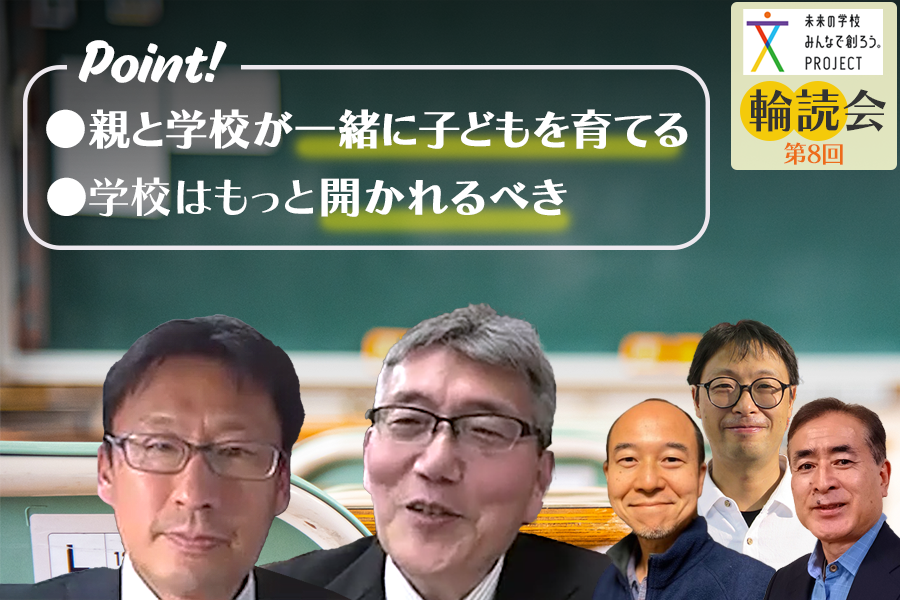
「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第8回 ゲスト:加藤 正人先生 小島 大樹先生
2024.07.29

「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第7回 ゲスト:酒本 絵梨子先生
2024.07.02