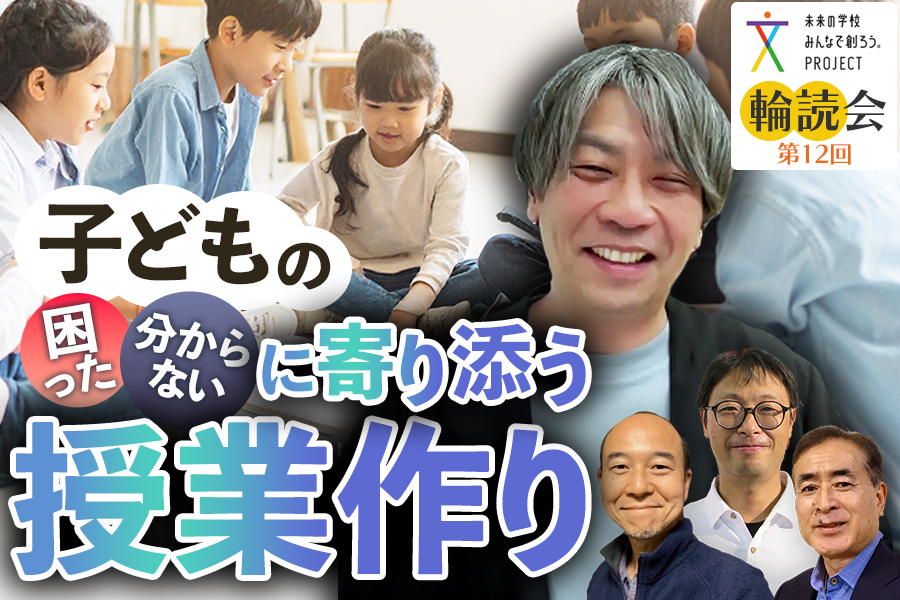
「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第12回 ゲスト:楳原裕仁先生(成城学園初等学校 教諭)
2025.08.20
 東京学芸大学公式ウェブマガジン
東京学芸大学公式ウェブマガジン「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
2025.10.08

100人輪読会 第13回のゲストは、成城学園初等学校の教諭、宮田諭志先生です。
宮田先生の実践の根幹には「子どもの今に注目する」という視点があります 。大人が子どもを自分に近づけるのではなく、「自分が子どもの方に寄っていく」という柔軟な姿勢を大切にしており、「〇年生だから」といった画一的な学年の枠で見るのではなく、一人ひとりの連続した成長として捉えることの重要性を語られました 。
授業においては、教師が一方的に知識を教えるのではなく、子どもに伴走し、共に喜び、悩む姿勢を重視されています 。単に結果を評価するのではなく、子どもが何かを発見した瞬間や、その過程で見せる「見方・考え方」を褒め、価値づけることが学びの質を高めるとしています 。
具体的な実践として、大学附属図書館や博物館などと連携する「S×UKILAM(スキラム)連携が紹介されました 。デジタルアーカイブ化された一次資料を用いることで、子どもが教科書にはない事実に自ら気づき、主体的に探究を深める学びが生まれています 。これは、子どもたちが本物の「社会的なものの見方、考え方」を発揮する良い機会となっています。
そのために不可欠なのが、教師や親以外の「サードパーソン」の存在です 。子どもにとって、多様な大人と関わることは心理的な安心感につながり、より自由な学びを可能にします 。教師もまた、多様な価値観を持つ人々と「つなぐ・つながる」ことで、より豊かな教育の場を創り出せると強調されました 。
宮田先生が最後に語る、未来の学校とは?ぜひご覧ください。
輪読会に参加された方:
●宮田諭志先生(成城学園初等学校 教諭)
●金子嘉宏先生(東京学芸大学教育インキュベーションセンター長 教授)
●荻上健太郎先生(東京学芸大学教育インキュベーションセンター 准教授)
●彦坂秀樹先生(東京学芸大学教育インキュベーションセンター 特命教授)
未来の学校 みんなで創ろう。Projectからの 「20の提言1st Season 2020~2022 ~完成しない、みんなで創り続ける学校を目指して」の詳細は、下記リンクからご確認いただけます。
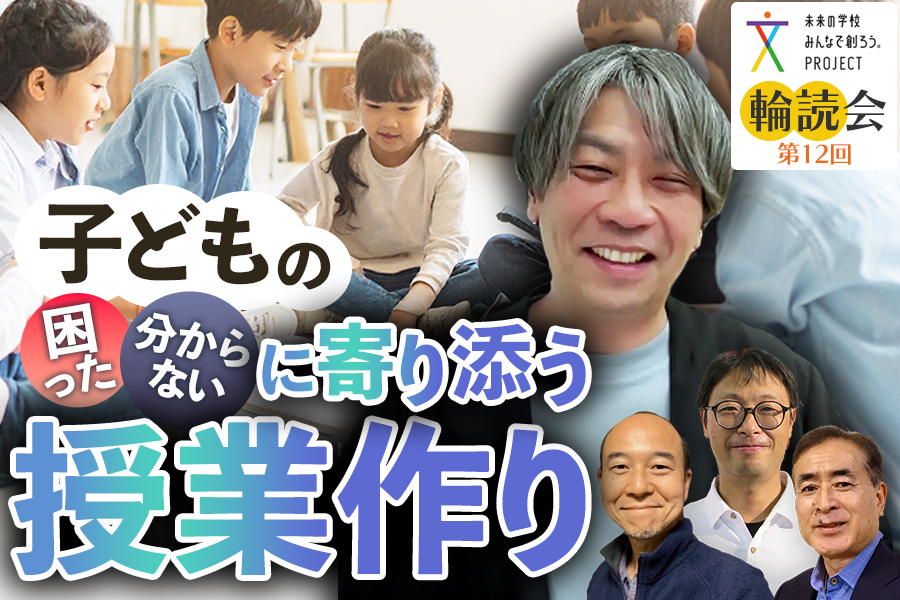
「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第12回 ゲスト:楳原裕仁先生(成城学園初等学校 教諭)
2025.08.20

「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第11回 ゲスト:小泉友先生(立川市立西砂小学校 教諭)
2025.04.22
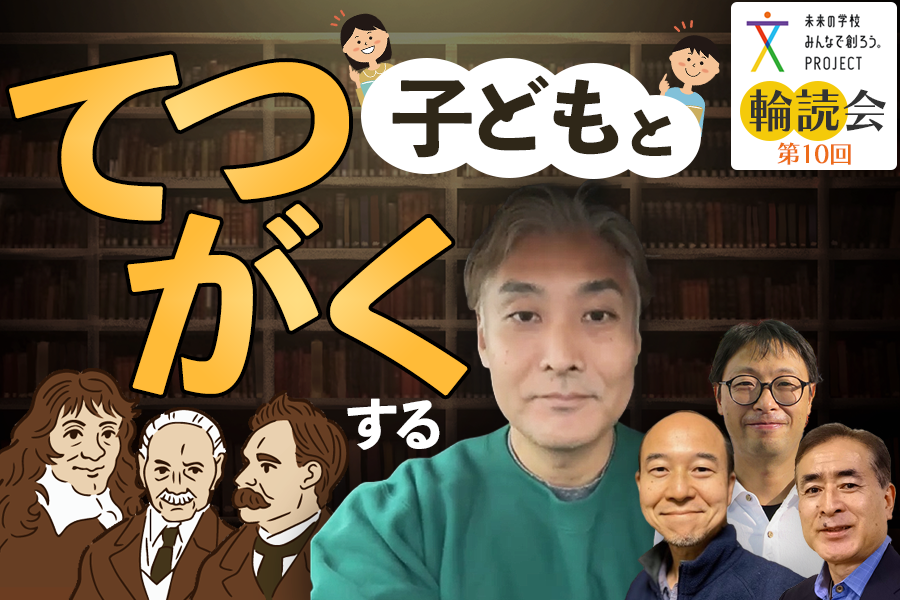
「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第10回 ゲスト:神谷 潤 先生(お茶の水女子大学付属小学校 教諭)
2025.03.18

「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第9回 ゲスト:下花剛一さん(株式会社ジョルテ 代表取締役 社長)
2025.02.05
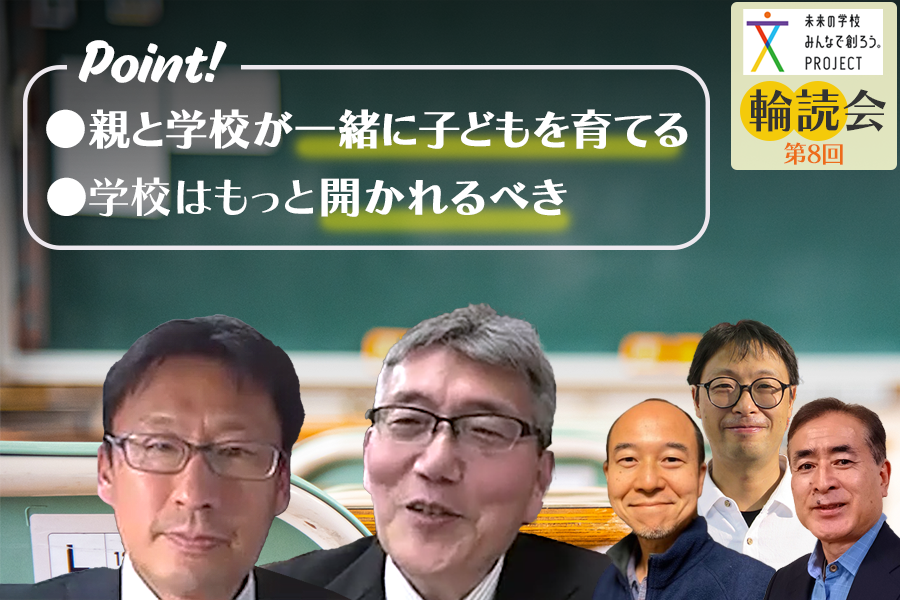
「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第8回 ゲスト:加藤 正人先生 小島 大樹先生
2024.07.29

「完成しないみんなで創り続ける学校を目指して」100人輪読会
100人輪読会 第7回 ゲスト:酒本 絵梨子先生
2024.07.02