
edumotto+
リカレント教育で学校現場に新たな風を
2026.02.17
 東京学芸大学公式ウェブマガジン
東京学芸大学公式ウェブマガジンedumotto+
2025.07.25

これまでedumottoで2回にわたり紹介した、名護こども食堂。2024年に「さくら教室」へと名称を変えたこの場所から、「琉球黄金もち麺」が発売された。
「琉球黄金もち麺」は乾麺の商品だ。麺は国立沖縄工業高等専門学校の学生が開発し、パッケージは東京学芸大学の学生がデザインした。名称、味、パッケージデザインにはさくら教室の子どもたちの意見を取り入れ、売り上げは教室の運営費になる。
本記事では、このような取り組みを始めとして、運営費がボトルネックとされるこども食堂の自走を目指して奮闘する大人たちと、自分なりの関わり方を模索した学生の声を紹介する。
名護こども食堂は、夜遅くに出歩く子どもたちを見かねた名護市営市場の人たちが始めた。しかしその運営は想いだけでは立ちゆかなかった。集まることで非行に走る子どもたち。膨らむ借金。開設から数年後に食堂を引き継いだ神谷康弘さんは「ご飯を食べさせているだけでは問題は解決しない」と感じた。そして立て直しのために、企業や大学の協力を仰ぐことにした。
その中で出会ったのが学芸大学だ。学内に設置されたこどもの学び困難支援センター(以下、sure)が関わることで、食堂は「子どもたちにご飯を食べさせるための場」から「教育学的なアプローチを交えながら、子どもの経験や学びを支える場」へと変わった。

自分の食事を準備する子どもたち。「教室」になっても食は大切な要素だ。
2024年には名称を「さくら教室」へと変更。名護は日本で一番早く桜が咲く地域なので「さくら」、そしてこの食堂の理念にふさわしい「教室」という呼称が採用された。
さくら教室の理念について、sureの田嶌大樹先生はこう語る。「その時々に子どもが最高に楽しめることをやる。そこでみえるこどものキラキラした姿や行動変容を見逃さず、その価値をみんなで共有していく。大人が押しつける『勉強』では、子どもとの信頼関係は築けない」。ここで歯の磨き方を教わるまで、自分で歯磨きをしたことがなかったという子もいるという。この場における「経験」「学び」の意味は重い。
こうして活動内容が変わった今、残る課題は運営費だ。現在さくら教室が自足できているのは、運営費の8%程度。その他は企業や個人の寄付に頼っている。「将来的には30%を自分たちでまかないたい」と神谷さんは語る。
神谷さんを食堂存続に駆り立てたのは、地元の大学生の存在だった。「子どもたちにとって大学生は、ロールモデルになり得る存在。活動に関わってもらうようになってから子どもたちの様子が変わった」と語る。
学芸大学4年(2025年3月当時)の関夏奈さんは、1年生の時からオンラインで活動に参加している。特技である絵を活かして子どもと関わってきた。「絵しりとりを通して交流してきた子が、進学するときに制服を見せてくれたのがうれしかった」と4年間の活動を振り返る。

A類美術選修の関夏奈さん。自身がデザインしたパッケージたちと一緒に。
関さんはこれまで、さくら教室のロゴマークや、「沖縄Tacoスパ!!」「黄金素麺」といった商品のパッケージをデザインしてきた。これらは全て、さくら教室との協働によって生まれた商品だ。今回の「琉球黄金もち麺」のパッケージもデザインした。「わたしは“ふつう”に暮らしてきた。ここにはいろいろな子どもがいる。この商品を買うことで、彼らの存在に目を向けてほしい」と語る。
「買って食べて支援する この選択がいつかあなたを食べさせる」。これは、さくら教室と地元企業や高等教育機関の協働によって生まれた商品のキャッチコピーだ。
貧困をはじめとした負の世代間連鎖を断ち切るために。そして支援を受けた子どもたちが、巡り巡って未来の社会で生きる人々を助けてくれるように。このキャッチコピーには、さまざまな立場の人が交わるこの場所で、悩みながらも自分なりの関わり方を見つけ出してきた――そんな、さくら教室に関わる人々の想いと願いが込められている。

「琉球黄金もち麺」のおすすめの食べ方はジャージャー麺。もちもちとした太麺は味の濃いソースとよく絡む。
「琉球黄金もち麺」の購入はコチラから!
https://75kids.base.shop/
一面的に語られがちなこども食堂の背景に、実は多様な取り組みがあるということを知った取材だった。さまざまな人の想いが交錯しつつ、ひとつの商品ができあがっていく様子はまさに協働そのもの。この記事が少しでもそこにいる人々の想いを伝え、支援の輪の起点となることを願っている。
<関連記事>
これまでのさくら教室の取り組みについて知りたい方はコチラ!
<関連動画>
麺を開発した高専生が語る「琉球黄金もち麺」ができるまで
取材・文/岩田有紗
取材協力・画像提供/ 東京学芸大学こどもの学び困難支援センター
さくら教室の取り組みについてのお問い合わせは、info@suretgu.comへ

edumotto+
リカレント教育で学校現場に新たな風を
2026.02.17

edumotto+
小金井祭の魅力をたっぷりとご紹介!【プレイバック!小金井祭2024】
2025.10.24

edumotto+
「教員という役を生きる」~松下隼司先生に学ぶ、演じる教員の仕事術~
2025.08.26
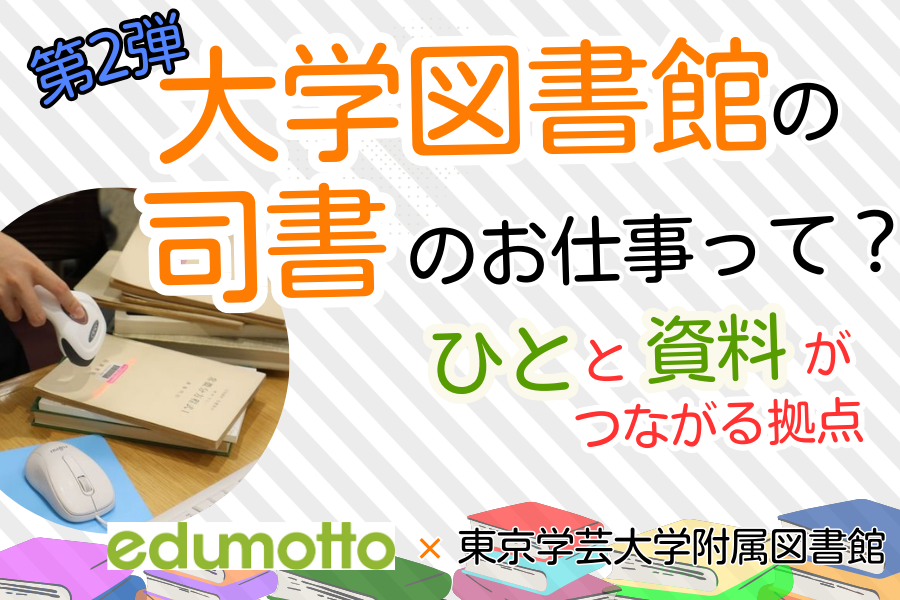
edumotto+
大学図書館の司書のお仕事って?〜ひとと資料がつながる拠点 edumottoメンバーが体験!~
2025.07.18

edumotto+
「教員養成大学ならではの知識の宝箱」東京学芸大学附属図書館ガイド
2025.03.21

edumotto+
柔道家 角田夏実選手が語る「準備力」~栄光を掴みとるまでの挑戦と勇気
2025.02.17